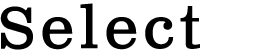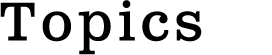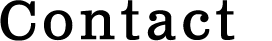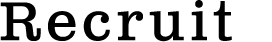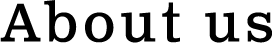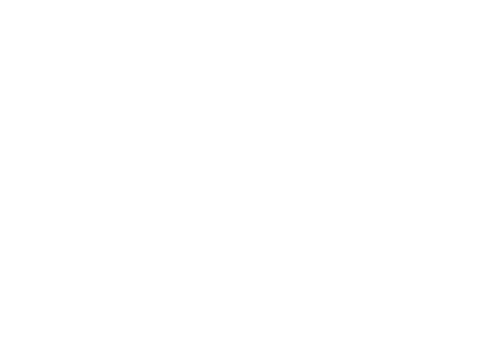皆さまこんにちは。株式会社Theatreの吉田です。
先日、私が「公認 不動産コンサルティングマスター(以下、不動産コンサルティングマスター)」の資格登録をいたしましたことをお知らせいたします。
目次
資格について
不動産コンサルティングマスターとは、国家資格ではありませんが、公益財団法人不動産流通推進センターが国土交通大臣の登録を受けて実施する「登録証明事業」により認定する資格であり、法令に基づく他の資格とも関連している、準公的資格です。
平成5年(1993年)に不動産コンサルティング技能登録者として資格制度がスタートし、平成25年(2013年)より現在の名称に変更となりました。
また受験資格として、国家資格である「宅地建物取引士」、「不動産鑑定士」、「一級建築士」のいずれかの登録者であることが条件です。
加えて、試験合格後に不動産コンサルティングマスターとして登録するためには、受験資格登録者として5年以上の実務経験があること(3年以上5年未満の場合は推進センター指定の講習を修了すること)が要件となります。試験に合格するだけでは、不動産コンサルティングマスターの登録をすることができません。
試験は午前の「択一式試験」と午後の「記述式試験」の二つに分かれ、科目は前者が事業、経済、金融、税制、建築、法律の6科目、後者が実務、事業、経済の必修3科目に加え、金融、税制、建築、法律から1科目選択の計4科目という形です。
なお、私が受験をした令和6年度(2024年)の試験の合格率は41.8%とのことでした。
不動産コンサルティングマスターの業務領域
現行の制度を形作った、国や都道府県、不動産業界団体らで構成された「不動産コンサルティング制度検討委員会」において取りまとめられた『不動産コンサルティング制度検討委員会報告書(平成11年9月)』では、以下のように定義されています。
「依頼者との契約に基づき、不動産に関する専門的な知識・技能を活用し、公正かつ客観的な立場から、不動産の利用、取得、処分、管理、事業経営及び投資等について、不動産の物件・市場等の調査・分析等をもとに、依頼者が最善の選択や意思決定を行えるように企画、調整し、提案する業務」
もう少し私たちの身近な言葉に言い換えるのであれば、例えば保有している不動産の価値をどう高めるか(維持するか)、相続時にスムーズに手続きが進められるように、どのように不動産を整理しておくことが良いか、それらを依頼者が最善の意思決定をするためにサポートをする業務とも言えます。
また不動産ファンドなど、大きな資本で不動産投資する場合において、さまざまなスキームを活用したコンサルティングを行うことも重要な業務となります。
私の考え・今後について
資格試験の概要や資格の定義の話しなど、やや細かく、堅苦しい説明をしてしまったかもしれませんが、個人的には大切な部分と思いあえて書かせていただきました。
不動産のニーズは多様化しており、「買いたい・売りたい」、「借りたい・貸したい」という言葉だけで考えても、その中には人それぞれ異なる状況や目的などの色があります。また生活する上で切り離すことはできない不動産について、私たちはどこかしらで向き合わなければいけない時がくるはずです。
不動産投資に積極的ではない方であっても、実は身内の家が空き家になっている(または将来空き家になる可能性がある)ということもあるかもしれません。
一方で、意外と周りに不動産について相談できる人がいないという声も耳にします。いたとしても、異なる不動産の分野で知識が乏しかったり、またお金が絡む話しでもあるため、適度な距離感のある人の方が相談しやすいという方もいるでしょう。
今まさにお悩みを抱えている方から、ふとご自身の不動産のことについて考えたいと思った方まで、弊社ではご相談に乗れる環境を整えてまいります。
月並みな言葉ではありますが、資格取得、登録はスタートであり、実際の貢献ができてこそ、価値があるものと考えております。これからも研鑽を続けてまいります。
最後までお読みいただきありがとうございました。