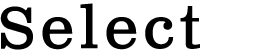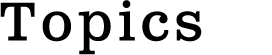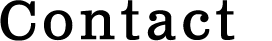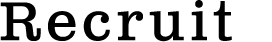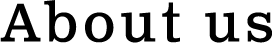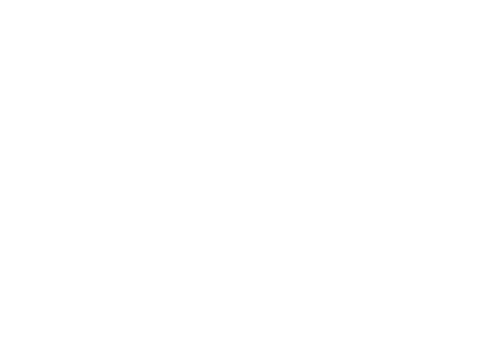皆さまこんにちは。株式会社Theatreの吉田です。弊社では、新たに法人を設立し自社のオフィスを構えたい、また新しく借りたオフィスで法人設立登記をしたいというご相談いただく機会も多いです。
今回は新たに法人を設立された(または設立予定の)方向けに、新たにオフィス借りる時の流れやポイントについてお話しをさせていただきます。
目次
法人を新たに設立された方へ
法人の設立、誠におめでとうございます。
設立へ至る経緯は様々ですが、そのご決断に寄り添えるよう、できる限りお役に立てればと思います。
今回はオフィスを借りる流れについてのご説明です。途中から新設法人ならでは項目が出てきますので、その点は特に注意しつつ読み進めていただけたらと思います。
物件探し
こちらは新設法人だけ特別ということはありません。
信頼できる不動産仲介会社へ相談されたり、ご希望エリアや賃料、広さなどをポータルサイトや不動産会社の自社サイトなどでお探しする形がスタートかと思います。
ただ、この後お話しする審査の進め方の問題もありますので、個人的には一度早めに不動産会社へ相談しされることをおすすめします。
適正賃料の考え方
個人名義で住宅を借りる場合は、名義人の年収から算出した月額賃料を目安として物件を探すことも多いかと思います。
しかしながら、オフィス等の事業用物件を借りる際、賃料は数ある経費のうちの一つですので、必ずしも「売上(見込)の何%」という考え方で審査をするとは限りません。後述する事業計画書などと照らし合わせながら審査は進みます。
適正な賃料について判断が難しいですが、特に大手資本などが入るわけでもなく、ご自身の自己資金のみで初めて法人を設立される方は、設立後に想定外の出費が発生する可能性も考慮して、資金繰りの状況や心理的にも過度な負担にならない程度の賃料が良いのではないかと思います。
物件申込・審査
内覧後の申込、審査がどれだけスムーズに進められるかが、契約、入居をトラブルなく進める上で非常に重要と考えております。
社歴の長い会社と比べ確認事項が増えるため、自社についてより理解してもらえる担当者かどうかも大切です。
ちなみに住宅の場合は、申込書提出の先後で厳密に番手を決めるという慣習が、今も業界内に広く定着しています。一方事業用物件においては、提出のタイミングも大切ですが、利用用途や業種、人の出入りの頻度、利用人数など、住宅よりも多くの事項を考慮した上で、貸主が最終判断をするという流れになります。
スピード感も大切にしつつも、申込内容を固めて、担当者と審査通過までのストーリーを共有してから申込む方が結果的にプラスに働くこともあると、ぜひどこか頭の片隅に留めていただければと思います。
むしろ申込書の提出スピードを意識しすぎて、事業の中身や使用方法の説明内容が頻繁に変わる、レスポンスが極端に遅い、申込後の条件交渉などの対応姿勢によって、オーナーからの心証が悪くなってしまう可能性もあるので、ご注意ください。
入居審査必要書類
可能でしたら、物件探しと並行して、事前に申込名義(=契約名義)と審査時に必要な書類については、仲介会社へ事前に相談しておくことをおすすめします。
契約名義は、法人を設立済みでしたらその法人名義で、申込物件で設立予定でしたら法人の代表予定者の個人名義で進めることが多いです。なお後者について、法人設立後に個人から法人への名義変更をご希望の場合は、事前に伝えておくことをおすすめします。事前に伝えているか否かで、名義変更に伴う費用が変わる可能性がありますのでご注意ください。
以下が一般的に求められる審査書類です。
【法人名義の場合】
1.法人登記簿謄本
2.会社概要
3.事業計画書
4.事業資金がわかるもの(通帳の残高証明など)
5.代表者身分証明書写し(外国出身の方は「在留カード」も)
など
【個人名義の場合】
1.身分証明書写し(外国出身の方は「在留カード」も)
2.収入証明書(確定申告書、源泉徴収票、課税証明書など)
3.事業概要
4.事業計画書
5.事業資金がわかるもの(通帳の残高証明など)
など
事業計画書
決算書が提出できないため、ここでどれだけ納得感のある資料を提出できるかが大切です。
内容次第ではこの資料でお客様の人柄も十分に伝わりますので、力と心を込めて作成されることをおすすめします。
形式は問いませんが、以下のような項目が含まれていると全体的にまとまりが出るのでご参考にしてみてください。
資金調達の準備で既に作成済みの方は、そちらをご提出いただく形でも結構です。
【事業計画書の記入項目例】
1.会社概要(商号・設立年月・資本金・代表者名など)*法人設立前の場合は予定を記入
2.事業概要
3.取扱商品・サービス
4.代表者プロフィール
5.実績(取り組んだビジネスについて)
6.主要取引先
7.売上計画・今後の見通し(数字面は3年先くらいまで)
など
連帯保証人
近年は保証会社を利用するのみで、連帯保証人なしの契約も増えてきましたが、オーナーによっては、連帯保証人を必ず立ててほしいと言われるケースがあります。
ここでは主に連帯保証人を求められるケースについて共有いたします。
1. 契約名義:法人 連帯保証人:法人代表者
比較的多いパターンです。ご自身で会社を作られた方にとっては、ご自身一人のみで契約が完結します。一方、法人オーナー以外の方が代表者(いわゆる雇われ社長)の場合は、連帯保証人となることに抵抗があるかもしれません。その場合は、不動産会社の担当者に相談しながら最適な方法を探ってください。
連帯保証人の必要書類として、個人の収入証明書や印鑑証明書の提出を求められることが多いです。
2.契約名義:法人 連帯保証人:法人代表者とは別の方(親族、知人など)
設立直後で法人のオーナーと代表者が同一人物の場合、代表者が連帯保証人になってもあまり意味がないと言われることがあります。その場合、別の方を求められます。お仕事をされている親族の方が優先で、どうしても難しい場合は知人の方でというケースもあります。お客様にもよりますが、直接事業に関わらない方へ連帯保証人を依頼することに抵抗がある方は多いです。こちらも不動産会社と相談しながら進めると良いと思います。
3.契約名義:個人 連帯保証人:契約名義人の親族、知人など
契約予定の物件で法人設立予定や、個人事業主として活動する場合は、契約名義は個人名となります。連帯保証人の属性は上記2と同様です。法人設立後、賃貸借契約を法人に切り替え、連帯保証人を代表者にすることで、契約時に設定した連帯保証人が外れるケースもあります。
先ほども申し上げましたが、近年は保証会社を利用することが多いです。保証会社との保証委託契約を結べば、賃貸借契約書上の連帯保証人は不要という形です。ただ一点、保証会社との契約では代表者が連帯保証人になって欲しいというケースはあります。賃貸借契約と混同しがちな部分ですので、この点も募集資料や不動産会社の担当者にも確認しながら進めていただければと思います。
契約・入居
契約内容が問題なければ、求められた必要書類を準備し、契約締結、契約金の入金をすれば、あとは鍵の引き渡しを待つばかりとなります。
審査対応まで関係者とうまくコミュニケーションを取りつつ進められれば、ここから大きなトラブルとなることは少ないです。仮にあったとしても、きっとお互い誠意を持って対応すれば、良い解決方法が見つかるかと思います。
おわりに
できる限り簡潔にまとめたいと思いつつ、この文量となってしまいました。。
ただこの流れを大まかにでも知っておいていただければ、物件も決まりやすくなります。
社歴の長い会社や、個人の住宅の契約と比べると、聞かれることが増え、提出書類も増え、面倒と感じる部分もあるはずです。ただ誠実に丁寧なコミュニケーションをとることで、新しいチャレンジを応援したいというオーナーに巡り合うことができ、きっと後押しもしてくれるでしょう。ぜひ頑張ってください。
ここで説明したことでもう少し詳しく聞きたい、他に相談したいことがあるという場合は、どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。
最後までお読みいただきありがとうございました。