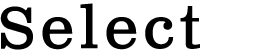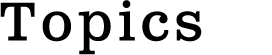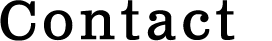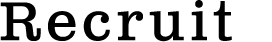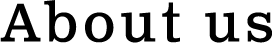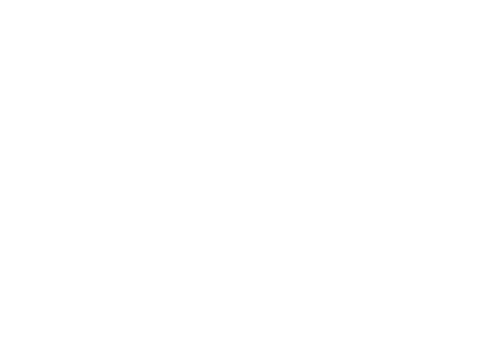目次
テーマ: 中東パビリオンの建築から見る文化的必然性
レポート概要
本レポートでは、大阪・関西万博2025における中東4カ国(UAE、カタール、サウジアラビア、バーレーン)のパビリオンを実地調査し、各国が伝統的・文化的な資源をいかにして現代建築技術と組み合わせた新しい形で表現し、万博全体のテーマである「いのち輝く未来社会のデザイン(Designing Future Society for Our Lives)」にどのように答えているかを考察した。
結果、「文化的アイデンティティの表現」と「サステナブル技術の統合」、「体験型の表現」という3つの共通点を持って取り組んでいることが分かった。
なお、本レポートにおける「文化的必然性」とは、各国の伝統文化が単なる飾りではなく、その国のアイデンティティの根幹をなすものであり、建築表現において必然的に取り入れられる要素であることを意味している。
UAEパビリオン:「Earth to Ether」
大地から天空へ

設計:Earth to Ether Design Collective(ATELIER BRÜCKNER )
建築面積:2,013 m²
出典:UAE Pavilion Expo | ATELIER BRÜCKNER 、datecrete

フィールドレポート
UAEパビリオンは入場と同時に、圧倒的な存在感を放つ90本の人工のヤシ柱が来訪者を迎える。この「ヤシの森」は単なる装飾ではなく、UAE固有の文化であるナツメヤシを使った「アリーシュ(ヤシ葉を編んで作る伝統建築)」を、現代的にリメイクした演出である。
柱材には、ナツメヤシの果実であるデーツ廃棄物を再資源化した素材が使用されており、触れると独特の質感を持つ。従来のコンクリートと比較して約30%の軽量化を実現しつつ、高い断熱性能を保持しているそうだ。

館内では伝統技術だけではなく、UAEの先端技術やサステナビリティへの取り組みについても体験することができる。
宇宙や医療の分野での功績を、映像やインタラクティブなアート、空間全体を使った展示で紹介している。
文化的必然性の分析
UAE文化において、ナツメヤシやデーツは単なる資材や食材ではなく、砂漠における生命の象徴である。ヤシ葉を編んで作る伝統建築の現代的再解釈により、「過去から未来への連続性」というコンセプトが空間体験として具現化されている。
カタールパビリオン:「Connection of Seas」
海岸線からの発展

設計: Kengo Kuma & Associates × Qatar Museums
建築面積: 1,111 m²
出典:Expo 2025 Qatar Pavilion、From the Coastline, We Progress

フィールドレポート
カタールパビリオンの最大の特徴は、伝統的なダウ船(帆船)を模した木製のフレーム構造が水上に浮かんでいる視覚的インパクトである。
隈研吾氏が手掛けたこのパビリオンは、氏の代名詞である木組み技術と、建物を覆う帆のような白い膜の組み合わせにより、カタールの海洋文化と日本の建築美学の融合を象徴している。

文化的必然性の分析
カタールのアイデンティティの根幹である「海」との関係性が、ダウ船というアイコンを通じて直感的に伝わる設計である。
館内ではカタールの真珠採取の海洋文化について、単なる歴史展示にとどまらず、インタラクティブで没入感のある演出の中で学ぶことができる。建築空間そのものが海洋体験を提供する仕組みは、文化の本質的理解を促していると感じた。
サウジアラビアパビリオン:「Living Community」
より良い未来のために一緒に

設計: Foster + Partners
建築面積: 3,542㎡
出典:Foster + Partners reveals village-like Saudi Arabia Pavilion with meandering streets at Expo Osaka、designboom

フィールドレポート
サウジアラビアパビリオンは、他の3カ国とは対照的に「コミュニティ」の概念を空間化した設計である。集落と市場の有機的な街並みを現代建築で再現し、曲がりくねる通路が来訪者を自然に中央広場へと誘導する動線設計になっている。
建物全体が一つの「村」として機能し、各エリアが異なる文化体験を表現している。日中は自然通風システムによる省エネ設計が効果を発揮し、夜間はパフォーマンス空間として劇的に変貌する多機能性を持つ。
特に注目すべきは、解体・再配置を前提とした構造設計である。万博終了後の利用を見据えた「ポスト博覧会建築」のモデルケースとして、持続可能性への配慮が随所に見られる。

文化的必然性の分析
サウジアラビアのホスピタリティ文化が、建築空間を通じて体験できる設計哲学が貫かれている。単なる空間展示ではなく、来訪者が実際にコミュニティの一員として参加できる仕組みは、同国の文化的価値観を伝える効果的な手法である。
バーレーンパビリオン:「Anatomy of a Dhow」

撮影: © Lina Ghotmeh Architecture
出典:Expo 2025 Official Participant
海をつなぐ―五感で巡る旅
設計: Lina Ghotmeh Architecture
建築面積: 998㎡
出典:Anatomy of a Dhow, Bahrain Pavilion Osaka Expo 2025 / Lina Ghotmeh Architecture、ArchDaily

フィールドレポート
バーレーンパビリオンは、伝統的なダウ船の骨組みを木造建築として再現している。海風を利用したパッシブクーリングシステムを内蔵し、機能性と美学が表現されている。
木造建築の内部では余分な装飾を排した空間で、真珠採取道具とダウ船の模型が展示される。過度な装飾を排除した空間構成により、来訪者の注意が本質的な文化内容に集中する効果が生まれている。
建築家Lina Ghotmehの設計による曲線的な木組みは、日本の伝統的木工技術との対話を意識したディテールが随所に見られ、両国の職人文化の共通性を表現している。
文化的必然性の分析
伝統的な真珠採取やダウ船建造はUNESCO 無形文化遺産にも登録されており、本パビリオンはバーレーンの文化的必然性を純粋に表現している。
サステナブル建築技術と伝統工芸の融合においても、装飾的な要素を排除したアプローチが取られており、持続可能性への取り組みが感じられる。
4カ国に共通する設計哲学
1. 文化的アイデンティティの建築的表現
4カ国すべてが、自国の核となる文化的要素(ヤシ、船、村、真珠)を単なるモチーフではなく、建物の構造や機能として組み込んでいる。これにより、表面的な装飾を超えた本質的な文化表現を実現している。
2. サステナブル技術の統合
廃棄物の再資源化(UAE)、自然エネルギーを活用した設計(バーレーン、サウジアラビア)、解体・再利用前提の設計(サウジアラビア)など、各国が持続可能性を文化的文脈の中で実現している。
3. 体験型の表現の重視
従来の展示型パビリオンから脱却し、来訪者が文化の当事者として参加できる体験型設計を採用している。これにより、文化理解の深化と国際的な共感を生み出している。
結論
中東4カ国のパビリオンは、それぞれ異なるアプローチながら、「文化的必然性に基づく建築革新」という共通の哲学を体現している。伝統的な文化資源を現代技術で再解釈し、持続可能性と異文化対話を実現するこれらの試みは、万博というプラットフォームを超えて、未来の建築や街づくりに新たな視点を提供している。
とりわけ、サウジアラビア・パビリオンは解体と再配置を前提にした構造により、会期後にも活用できる持続可能な建築モデルを示している。
本視察を通じて確認されたのは、建築が単なる構造物を超えて、文化の翻訳装置として機能する可能性である。中東4カ国のパビリオンは、この可能性を最大限に活用し、来場者がその文化をじっくり味わいながら、これからの社会のヒントもつかめる仕掛けになっている。
編集後記

数年前、トルコを旅した際に初めて触れたイスラム文化、壮大な歴史の物語を宿す宗教建築とタイルやアラビア文字の装飾に息を呑んだあの日の感動が、いまも私の心に鮮やかに残っています。その体験をもう一度味わいたく、今回は中東パビリオンを中心に視察。
悠久の歴史が最新の建築技術やデジタル演出とどのように結びつくのか、その現場を自分の目で確かめることが目的でした。
私が大阪・関西万博に訪れたのは4月後半。まだ公開前だったパビリオンも多く、今はさらに見応えが増しているはずです。会期は10月13日まで続きますので、もしもう一度行けるなら、次は中央アジアのパビリオンを中心に巡ってみたいと思っています。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
皆さんもぜひ会場で、思いがけない発見を楽しんでください。