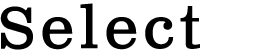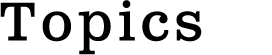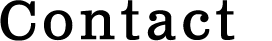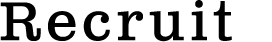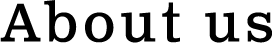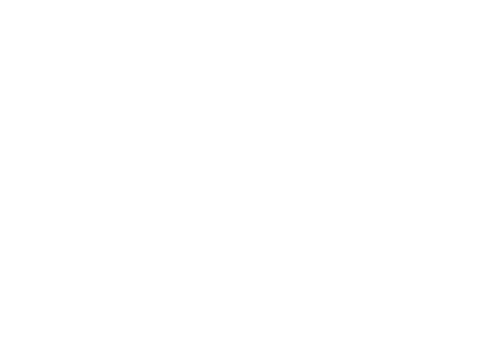皆さまこんにちは。
Theatreの山田です。
今回は2024年12月に福島県の浜通りに位置する南相馬市小高区、双葉郡浪江町を訪れ、ゼロからはじまったまちづくりや新しいことに挑戦する人々に出会いました。
このコラムでは、浪江町(なみえまち)にある東日本大震災の際に建てられた仮設住宅を再利用をしたシェアプレイスについてお話ししています。この地にゆかりのある方もそうでない方も東日本大震災から13年経った被災地での取り組みを知るきっかけとなれば幸いです。
きっかけは毎日に豊かさを感じて過ごす生活がしたいと思っていたある日、たまたま帰宅中のSNSで『遊ぶ広報』という暮らすようにまちに滞在しながら、心が動いた瞬間をSNSに発信していくというプログラムを見かけ、早速その日のうちに応募して12月の初旬まだ少しあたたかさが残る福島県へ向かいました。
福島県の浜通りは未だ震災や原発事故の爪痕が残っており、東日本大震災から13年経った今、はじめて震災やまちについてきちんと知る機会となりました。実際に2日間過ごし、沢山の面白いものや素敵な人が集まる場所、色んな人が集まり挑戦している様子から明るく豊かな生活がここでは流れていると感じました。
タイトルである”繋がる、新しい風景”とは私がここ(福島県浪江町、南相馬市小高)で感じた人と人の繋がりやそこに集まった人たちの挑戦を表しています。震災後、元々このまちに住んでいた人の多くは現在は別のまちへ移住しているケースが多いとのことですが、一方でゆかりのないこのまちに新しく移住を決めた人も多いそうです。そんな新たな住民が始めているまちおこしは非常に興味深く、カフェやコワーキングスペースなど多岐に渡ります。
その中で今回は遊ぶ広報のアテンドツアーでご案内いただいた施設であるSTUDIO B-6さんをご紹介させていただきます。ぜひ最後までご覧ください。
目次
STUDIO B-6

震災のときに建てられた仮設住宅を再利用した事務所兼コミュニティスペース。
建物自体は東日本大震災のときに建てられた木造の仮設住宅であり、震災時に建てられた応急仮設住宅を浪江町へ移設し、再利用され完成した建物です。仮設住宅自体の解体は震災からおよそ10年後に行われ、震災の被害の大きさを表しているように感じます。
再利用の施工時には、木造丸太組工法という、軸組・外壁・外壁下地がログ材による同一部材であることで、 熟練の職人による施工体制を必要としない簡易な施工性を活かし、ログ材を積み上げたそうです。その他も要所以外は、 基本的には設計者のセルフビルドによって施工されています。

木造丸太組工法

移設前の仮設住宅の様子

左下のプレートは仮設住宅当時の番号プレート
4つの住戸が入っていた仮設住宅1棟の内壁を取り外し、一続きになっている空間は日中は日が差しとても心地のいい空間でした。ひとつの空間にいる感覚を残しつつそれぞれの空間ではモノによって雰囲気や流れる時間が分かれています。
メインは建築設計事務所のアトリエとして使用されており、入り口正面のスペースでは浪江町の地域おこし協力隊の方によって本屋さんが開かれています。またその横のスペースではコーヒーなどを楽しめるカフェを開くことを考えているそうです。また、DJなど音楽を聞く集いやZINEを作る会などが定期的に行われている空間になっているようです。

一続きになっている4つの空間
住所:〒979-1531 福島県双葉郡浪江町川添佐野51−4
サイトURL:https://fimstudio.jp
Instagram:https://www.instagram.com/studiob6_namie/
コウド舎

先ほどご紹介したSTUDIO B-6内にある本屋コウド舎さん。浪江町へ地域おこし協力隊として移住した佐藤さんが営む本屋さんです。主に浪江町に関わる方々から預かっている本が並んでおり、古書店のような雰囲気もあります。
営業時間:月火金土 11:00〜18:00(最新の情報はInstagramにてご確認ください)
サイトURL:https://ko-do-sya-namie.stores.jp
Instagram:https://www.instagram.com/ko_do_sya_namie/
今回の訪問の振り返り
2011年に発生した東日本大震災、当時小学生だった私はこの日、このまちを訪れるまでここで起きた震災や原発事故について知ることをせずにいました。今回の訪問ではアテンドツアーでまちを案内してくれたみなさんがここでの震災についてやこれからのまちのことについて丁寧に教えてくださりました。カタチはそのまま、色を変えて新しく価値を生み出そうと活動するまちの人たちに出会い、とても刺激を受けた2日間でした。
またいつか訪れることがありそうな、いつの間にかそこにいるような感覚がのこるまち。
ここでの生活はきっととても豊かであると感じました。
フォトギャラリー